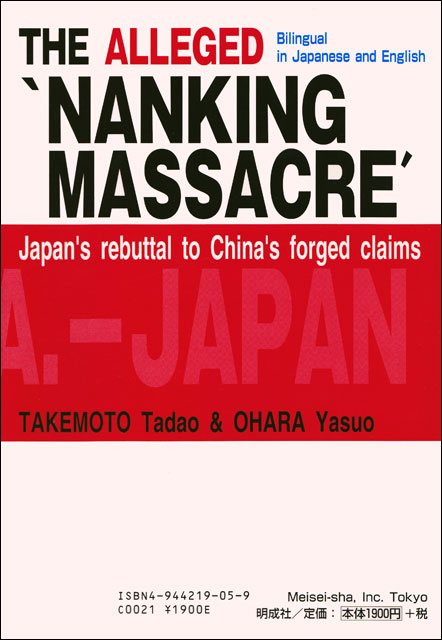竹本忠雄 アメリカ人への手紙
が、まあ、よかろう。であればこそ、再告発に応えて、我々のほうこそ、再審を、むしろ望むところなのである。そして我々が、陪審員席に座するアメリカ人諸氏に期待するのは、言いたい放題の原告の言い分をさんざんに聞かされたあとで、今度は被告の言うことにも公平に耳を傾けていただきたいということなのだ。
殺人事件というなら、犯人がどこかにいるはずだ。死体はあるのか。目撃者は?殺しの動機は?
そもそも殺人とは、それによって利益を得る者が犯人と通り相場が決まっている。ホロコーストがあったというなら、それによって、いったい誰が利益を得たのだろう。
ヒットラーの場合は、アウシユヴィッツからプッヘンヴァルトに至る何十箇所のガス室によって、「種の優越」思想を証明するという利益を得ようとした。
「南京国際委員会」と各国ジャーナリストの監視の目が光る首都南京の真只中で、戦闘とはいえ、人口数を上勝る――かりにそれが可能だったとして――ほどの殺毅をやってのけることで、日本軍の得る利益などというものがあったのか。要するに、日本の文化に、そんなジンギスカンかアッティラ大王なみの殺戮をゆるす「元型」があっただろうか。「一木山草をも残さない」というような。
「ホロコースト」というなら、元々、中国にあったものこそ、それではなかったか。抵抗すれば城内の老若男女ことごとく抹殺しつくすことは、一種の国際法として、唐代以来、この国に認められていたことで、清朝にまで、それが続いてきたことは、その史書が証しするとおりである。「屠城」とそれを呼び、単なる城攻め「抜城」とは全然異なっていた。女は、ただ犯されるだけではない。裸にされ、髪の毛で梁に吊され、乳房を削ぎ取られる。何のことはない。これは、日本軍が来たらこうやられるぞと、蒋介石軍が、ぎごちない絵まで描いて宣伝ビラに仕立て、あらかじめ民衆にばらまいていたもののモデルであり、アイリス・チャンがおどろおどろしく書き立てたことの下敷ではないか。
けだし、文化とは、愛しかた、殺しかた、嬲りかたにまで現れるものであって、自国のその元型にないものは、特殊の狂人を除いては人は体系的にやりはしないのだ。にもかかわらず、なぜ、あえて中国人は、日本人にそれを仮託したがるのか。
西欧の心理学は、それを説明する用語を持っている。「レミニッサンス」であり、「投影」である。一千年間にもわたって祖先のやってきたことは、「無意識的記憶」すなわち「レミニッサンス」となって生きつづけ、相手にそれを「投影」せずにはいない。マクベスを駆り立ててライバルを殺される魔女のように。
「日本と中国は、愛の原理、死の原理、そして音楽の音階と、この三つにおいて根本的に異なっている」。
アンドレ・マルローのこの言葉が甦ってくる。「南京」は、一つの歴史のケースであるだけではない。比較文明論の絶好のモデルなのだ。
南京事件は、一見、きわめて複雑な殺人事件と思える。しかし、もし諸賢が、名探偵たるの条件、すなわち明察(claire voir)の心をお持ちであれば、クノックスの迷宮に分け入る「アリアドネの糸」が見えてくるのではなかろうか。アンチ・セミチズムを生んだ有名な偽書、『シオンの長老の議定書』があったごとく、アンチ・ヤマトイズムを生んだ偽書、『田中上奏文』があったごとき、それである。
1925年にソ連の国家保安部、GPE(KGBの前身)によって作成された「天皇承認済み」と称する「日本の世界制覇のプロジェクト」は、中国とアメリカを通して世界的に喧伝され、日中戦争が起こるや、中国ではエドガ-・スノーと組んだ宋慶齢を通して、また有名な西欧15人衆の「南京安全区国際委員会」を通してフル機能しはじめた。
そして南京から8年後、東京裁判の時いたるや、キーナン検事が「お前たちはそもそもの初めからして世界制覇のコンスビラシーをもって満州侵略と中国侵略を企てたのではなかったか」と責め立てるうえに、影の威力を発揮したのである。「A級」被告人らは目を白黒させるばかりだった。「夢にも思い及ばざること」と、呆気にとられて、東条は答えるほかはなかった。さすがに、聡明なる連合国判事団は、『田中上奏文』なるものは偽書だったと気づかざるをえなかったのである。